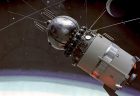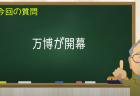4月13日 – 今日は何の日?

準備中でごめんなさい!
INDEX(目次)
ピックアップ TODAY!
日本最初の喫茶店「可否茶館」
1888年(明治21年)のこの日、東京・上野(下谷上野西黒門町)に日本初の本格的なコーヒー喫茶店「可否茶館(かひいさかん)」が開店。

明治16年(1883年)には鹿鳴館(ろくめいかん)が建設され、いわゆる「鹿鳴館時代」が始まったことで、欧化主義がもてはやされるようになり、珈琲(コーヒー)は、ハイカラな飲み物として、特権階級の人々の間で人気がありました。
その「可否茶館」の創始者は鄭永慶(ていえいけい)という人物で、上流階級が集まる鹿鳴館に対して庶民の共通のサロン、知識の広場の設立を理念としました。それは渡航経験で庶民が自由に気楽に交流できる場としてのコーヒーハウスをアメリカで実際に見てきたからでした。
そのため「可否茶館」は西洋館二階建ての中に、ビリヤード、トランプ、碁、将棋と娯楽だけではなく、更衣室、化粧室、シャワー室まで完備。さらに国内外の新聞や雑誌を置き、図書館を目指して各種の書籍や書画を自由に閲覧できるようにしてありました。
しかし、「可否茶館」は、3年もたずに閉店してしまいました。原因は価格で、もりそば1杯が8厘から1銭の時代にコーヒーが1銭5厘、牛乳入りコーヒーが2銭で、やはり当時の庶民にとっては高額でした。(現在では、スタバと立ち食いそばの料金は、逆転していますね。)
その後、1910年代の明治時代末から大正時代にかけて「カフェー」と呼ばれる喫茶店が全国的に普及し、日本において喫茶店ブームとなり、1950年代後半には音楽も楽しむことができる「ジャズ喫茶」「歌声喫茶」「名曲喫茶」などが流行しました。
時代ともに形をかえてきた喫茶店ですが、その初めての喫茶店「可否茶館」は、庶民がコーヒーを楽しめる歴史の分岐点になったことは間違いのないことですね。
以下の動画で、コーヒーの香りを楽しんでください。
歴史上の出来事
- 710年(和銅3年3月10日) - 元明天皇が藤原京から平城京に遷都。
- 744年(天平16年2月26日) - 聖武天皇が恭仁京から難波京に遷都。翌年平城京に戻す。
- 1179年(治承2年3月24日) - 平安京内で治承の大火(次郎焼亡)。三十数町が全焼。
- 1336年(延元元年/建武3年3月2日) - 南北朝時代: 九州に落ち延びていた足利尊氏が再び挙兵、多々良浜の戦いで南朝方の菊池武敏を破る。
- 1668年(寛文8年3月2日) - 宇都宮興禅寺刃傷事件が起こる。
- 1856年(安政3年3月9日) - 長崎・下田などの開港地での踏み絵を廃止。
- 1888年 - 東京・下谷黒門町に日本初のコーヒー専門店「可否茶館」が開店。
- 1903年 - 日本で小学校令が改正され国定教科書制度が取り入れられる。
- 1922年 - 少年団日本連盟(現在のボーイスカウト日本連盟)結成。
- 1923年 - 大阪鉄道の大阪天王寺駅が開業。
- 1940年 - NHKが日本初のテレビドラマ『夕餉前』の実験放送。
- 1941年 - モスクワで日ソ中立条約が締結。
- 1950年 - 静岡県熱海市で火災。強風により延焼して熱海市役所、熱海市警察署、消防署、旅館47軒を含む約1500棟が全焼。
- 1975年 - ロックバンド、キャロルが解散。
- 1982年 - 毎年8月15日を「戦歿者を追悼し平和を祈念する日」とすることが日本の閣議で決定。
- 1991年 - 東海大学安楽死事件がおこる。
- 1992年 - テレビ朝日系テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』放送開始。
- 1994年 - フジテレビ系刑事ドラマ『古畑任三郎』放送開始。同シリーズは2006年の正月の特番で終了するまで約11年続いた。
- 2001年 - 日本でDV防止法が公布される。
- 2011年 - 東日本大震災に伴う津波の被害により閉鎖されていた仙台空港が、一部の国内線において運行を再開。
- 2011年 - 大阪大学医学部附属病院で日本初の15歳未満がドナーの心臓移植が行われる。
- 2013年 - 午前5時33分ごろ、マグニチュード6.3の淡路島地震が発生。34人が負傷、8,000棟以上の家屋が損壊した。
- 2017年 - 南谷真鈴が北極点に到達。世界最年少で七大陸最高峰頂上・北極点・南極点の全てに到達する探検家グランドスラムを達成。
(Wikipediaより国内抜粋)
記念日・行事・お祭り
| 決闘の日 | 1612年(慶長17年)旧暦4月13日(新暦5月13日)、巌流島(船島)で宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が行われたことに由来します。 武蔵は約束の時間に2時間遅れて到着。怒った小次郎から振り下ろされた刀は武蔵の鉢巻の結び目を切っただけで、かわりに武蔵は船の櫓をけずって作った木刀で小次郎の頭を打ち砕いたといいます。 |
|---|---|
| 喫茶店の日 | 1888年(明治21年)4月13日、東京・黒門町(現在の台東区上野1丁目)に日本初の本格的な喫茶店「可否茶館(かひさかん)」が開店したことに由来します。 |
| 水産デー | 1901年(明治34年)4月13日、漁業生産についての基本的な制度を定めた「旧漁業法」が制定されました。これを記念して、(一社)大日本水産会が制定。 |
| 花キューピットの日 | 花キューピットは、全国どこからでも届け先近くの加盟店を通じて新鮮な花を贈ることができるサービス。2023年にサービス開始70周年を迎え、これまで以上に「花を贈る」ことで癒しや感動があふれる社会を目指していきたいと、(一社)JFTDが制定。日付は、前身の日本生花商通信配達協会の設立日(1953年4月13日)から。 |
| 浄水器の日 | 浄水器を信頼のおける家庭用品として定着させたいと、(一社)浄水器協会が制定。日付は「よ(4)い(1)み(3)ず」(良い水)と読む語呂合わせから。 |
本日の誕生日
4月13日には、松平信康(戦国武将)、トーマス・ジェファーソン(アメリカ合衆国大統領)、後藤象二郎(政治家)、徳川夢声(講談師)、大宮敏充/デン助(喜劇俳優)、吉行淳之介(小説家)、宮尾登美子(小説家)、藤田まこと(俳優)、松永真(グラフィックデザイナー)、ビル・コンティ(作曲家)、ローウェル・ジョージ(ミュージシャン)、森口祐子(ゴルフ)、上沼恵美子(タレント)、西城秀樹(歌手)、萬田久子(女優)、萬田久子(女優)、つみきみほ(女優)、水嶋ヒロ(俳優)、昴生(ミキ)が誕生しています。(敬称:略)