手形・小切手が遂に廃止 【髙橋洋一チャンネル#1240】
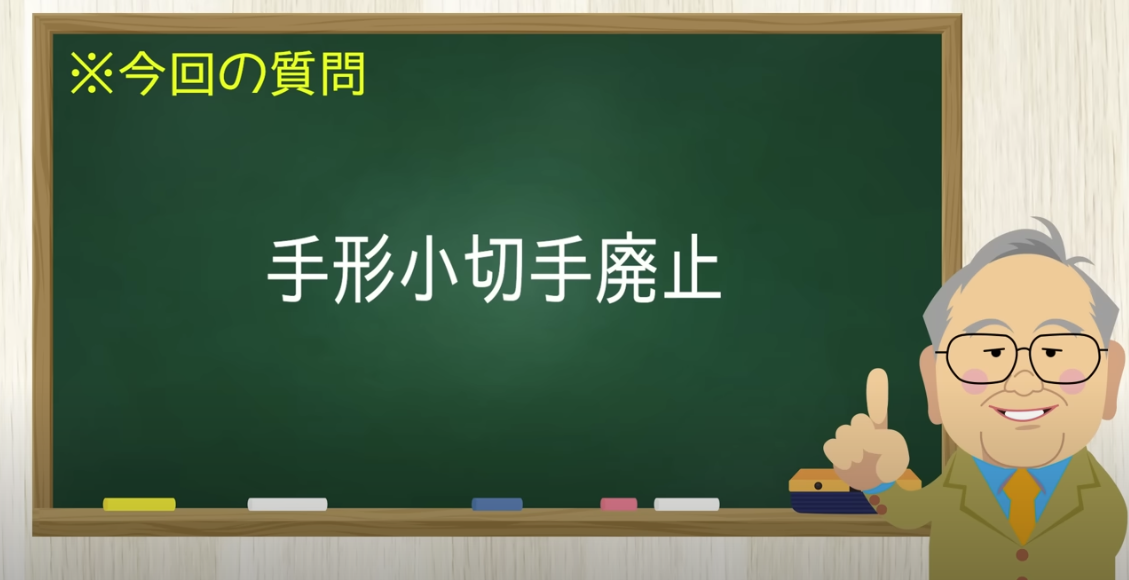
『髙橋洋一チャンネル」は、数量政策学者で嘉悦大学教授の髙橋洋一さんが視聴者の質問に答える形で、政治経済や世界情勢など現在進行中の問題について理路整然と解説してくれるYouTubeチャンネルです。
INDEX(目次)
手形小切手廃止
『高橋洋一チャンネル』の内容を要約
1. 手形・小切手が2026年度末で完全廃止へ
・手形・小切手は、かつて企業の資金繰りや決済手段として活用されていた
・1990年がピークで、その後取引量は激減。現在は当時の1.5%程度まで減少
・今では多くの企業が銀行振込で対応しており、使用する会社はほとんどない
・資金繰りで支払いを遅らせる利点もあったが、現在はメリットが薄れた
キーワード:手形、小切手、資金繰り、企業決済、電子化
2. アメリカ生活での小切手文化体験
・1998年から2001年のアメリカ生活では、小切手(チェック)が一般的な決済手段だった
・銀行でチェッキングアカウント(当座預金)を開設すると、小切手帳が配布された
・支払いの際には、金額を英語で手書きする必要があり、最初は非常に苦労した
・モータービークルサービス(免許関連)で初めて小切手を切った際には、記入ミスで怒られた経験も
キーワード:アメリカ、小切手、チェック、チェッキングアカウント、生活体験
3. チェッキングアカウントと公共料金支払い
・公共料金(電気・ガス・水道)は小切手で支払うのが一般的だった
・銀行口座から正しく引き落とされているか、毎月明細を確認する必要があった
・2~3か月に1度程度の頻度で記録ミスも発生し、銀行に訂正を求めることもあった
キーワード:チェッキングアカウント、公共料金、小切手、誤請求、銀行対応
4. 小売店での支払いとデビットカードの登場
・田舎の商店では小切手が使われていたが、都市部ではクレジットやデビットが主流に
・デビットカードは即時決済ができて便利で、対応店舗では積極的に使用していた
・現金を持ち歩かずに済み、チェッキングアカウントと併用して生活していた
キーワード:クレジットカード、デビットカード、小売店、即時決済、キャッシュレス
5. 電子決済時代の到来と小切手文化の終焉
・今ではスマホやネットバンキングで即時に送金可能となり、小切手の役割は消滅
・チェッキングアカウントや小切手は煩雑で、デジタル決済が簡単で合理的
・不正請求も経験したことがあり、電子化によるリスク低減も評価している
キーワード:電子決済、スマホ送金、ネットバンキング、チェック文化の終焉、合理化
6. 「でんさい」など電子記録債権への移行
・中小企業向けには、紙の手形に代わる「電子記録債権(でんさい)」が普及
・「でんさいネット」が運営し、従来の決済方法からの移行が促されている
・銀行振込やネットバンキングの方が簡便で、紙の手形は不要に
キーワード:でんさい、電子記録債権、手形廃止、中小企業、ネットバンキング
7. 政府小切手の廃止と給付の今後
・政府小切手も2026年度末で廃止される見通し
・過去に「政府小切手による商品券給付」を提案していたが、時代遅れに
・今後はマイナンバーに紐付けた口座に直接給付する「プッシュ型給付」が主流へ
・マイナンバーとの紐付けを拒否する人には給付が難しくなる可能性
キーワード:政府小切手、プッシュ型給付、マイナンバー、給付改革、商品券
8. 法改正と専門家の役割消滅
・手形・小切手の廃止により、「手形小切手法」の専門家の仕事もなくなる
・かつては専門書を執筆する法学者もいたが、制度の消滅で役割が失われている
キーワード:手形小切手法、法改正、制度廃止、専門職消滅、法律家
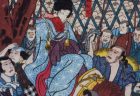

LEAVE A REPLY