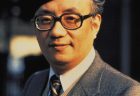4月6日 – 今日は何の日?

準備中でごめんなさい!
INDEX(目次)
ピックアップ TODAY!
環境問題化する「オリンピック」
1896年(明治29年)のこの日、第1回近代オリンピック大会がギリシャ王国アテネで開催されました。この大会は、古代オリンピックに感銘を受け、「近代オリンピックの父」とも呼ばれるフランスのピエール・ド・クーベルタン男爵により提唱され、世界的なスポーツ大会として開催されました。

この古代ギリシャに誕生し、今では4年に一度のスポーツの祭典として世界中の人々に親しまれているオリンピックですが、大きな金が動くこ商業的な意味合いが大きくなった結果、地球環境に影響を与えている側面があるといいます。
長い歴史の中で「経済発展や国家成長の象徴」としての目も向けられるようになったオリンピックですが、その開催地に選ばれた都市は、多くの種目のスポーツを行うためにグラウンド、選手村などを新たに建設する必要があります。
日本で1972年に開催された札幌五輪では、支笏洞爺国立公園にある国有林を伐採して、アルペンスキーの滑走路を建設しましたが、自然保護のため、大会終了後に滑走路など施設の解体と植林を工事費2億円以上をかけたとのことです。
1998年の長野五輪では自然の豊かさが残る志賀高原の岩管山がアルペンスキーの競技場候補に上がりましたが、自然保護連盟による反対運動により、幸いにも開発は中止となりました。
そして、2020年の東京五輪では、葛西臨海公園内にカヌー競技場の建設が予定されましたが、「多数の生息している水中生物の存在が危ぶまれる」との声が上がり、計画は白紙となりました。

日本の場合は環境問題と向き合い、調整をしていますが、ある近い国では冬季五輪を成功させるために、自然を改造し、雪のない山にほぼ100%の人工雪を無理に降らせたりと手段を選ばない方法をとりました。
ちなみに人工雪にヨウ化銀を使用すると氷の結晶化の効率が上がりますが、量によっては人体、植物に影響があり、実験段階でも少量しか使用できないのが現状です。しかも空気中のヨウ化銀が地面に到達し、やがて黄砂となって日本に飛来することとなります。
人工雪の問題はこちらのサイトで ⇒ 人工雪は冬季五輪を救う? – SWI swissinfo.ch
歴史上の出来事
- 1591年(天正19年2月13日) - 豊臣秀吉が千利休を京都から堺へ追放。
- 1633年(寛永10年2月28日) - 第一次鎖国令。江戸幕府が、奉書船以外で海外渡航・海外に長期在住した日本人の帰国を禁止。
- 1825年(文政8年2月18日) - 江戸幕府が異国船打払令(無二念打払令)を発布。
- 1868年(慶応4年3月14日) - 前日から続く2度目の西郷隆盛と勝海舟の会談により、官軍による江戸総攻撃の中止と江戸城の無血開城が決定[1]。
- 1868年(慶応4年3月14日) - 五箇条の御誓文発布[2]。
- 1882年 - 自由党党首の板垣退助が遊説中に暴漢に襲われる。(岐阜事件)
- 1921年 - 東京の浅草で大火。 住家や店舗1227戸全焼、同73戸半焼。市民が494人、消防隊50人が負傷。
- 1928年 - 多摩湖線国分寺駅〜萩山駅間で、西武多摩湖線開業。
- 1931年 - 東京放送局(現在のNHK放送センター)がラジオ第2放送を開始。
- 1941年 - 琵琶湖遭難事故: 旧制四高漕艇部員11名が琵琶湖で練習中に突風で遭難。流行歌「琵琶湖哀歌」の題材となる。
- 1944年 - 愛知県に大府飛行場が竣工する。
- 1952年 - 大村競艇場にて競艇が初開催される。
- 1955年 - 最高裁が、帝銀事件の平沢貞通の上告を棄却する判決。
- 1964年 - NHK総合テレビで人形劇『ひょっこりひょうたん島』放送開始。
- 1975年 - 朝日放送制作(NET→テレビ朝日系列)の『パネルクイズ アタック25』が放送開始。
- 1978年 - 東京都豊島区東池袋の旧東京拘置所の跡地に60階建の超高層ビル「サンシャイン60」の展望台がオープン。当時は東洋一の高さを誇った。
- 1978年 - 第1回日本アカデミー賞授賞式が行われる。
- 1978年 - 東京都練馬区中荒井で1時間に62mmの局地的強雨。神田川が下落合、高田馬場付近で氾濫して約580戸が床上浸水、床下浸水。石神井川が大谷口で氾濫して約200戸が床上浸水、約850戸が床下浸水。
- 1994年 - 死刑廃止を推進する議員連盟が発足。
- 2002年 - 多くの公立小・中学校、高等学校にて学校週5日制を適用。
- 2004年 - この年メジャー移籍した松井稼頭央(当時ニューヨーク・メッツ)がアトランタ・ブレーブス戦で、メジャー史上初の開幕戦・新人・初打席・初球本塁打を記録。
- 2023年 - 宮古島で自衛隊ヘリが墜落する
(Wikipediaから国内抜粋)
記念日・行事・お祭り
| 北極の日 | 1909年(明治42年)4月6日、アメリカの探検家ロバート・ピアリーが世界で初めて北極点に到達したとされていることに由来します。 |
|---|---|
| コンビーフの日 | 1875年(明治8年)4月6日、コンビーフの台形の缶(枕缶)がアメリカで特許登録されたことに由来します。 コンビーフは英語で「corned beef(コーンドビーフ)」といいます。「corned」は”塩漬けの”という意味であり、コーンドビーフは「塩漬けの牛肉」ということになります。もともとは保存食として長期航海や軍需用として利用されていました。 |
| アバの日 | 「S.O.S.」や「ダンシング・クイーン」など数々のヒット曲を生み出したスウェーデンの世界的なポップ・グループ「ABBA(アバ)」。アバの世界デビュー40周年を記念して、ユニバーサルミュージック(同)が制定。 日付は、1974年4月6日に英ブライトンで行われたユーロヴィジョン・ソング・コンテストにおいて、アバが「恋のウォータールー」で優勝したことから。 |
| 事務の日 | 日頃、縁の下の力持ちとして裏方に徹し、表舞台の営業職や広報・企画職などを支える事務職の労をねぎらいたいと、事務職啓発普及協会が制定。 日付は「じ(4)む(6)」(事務)と読む語呂合わせから。 |
| 開発と平和のためのスポーツの国際デー | スポーツが平和と開発を促し、寛容と相互理解を育むことに着目し、国連総会で制定。日付は、近代オリンピックの最初の大会(1896年アテネオリンピック)が開幕した日(1896年4月6日)から。 |
| 城の日 | 城を中心とする文化に関心や理解を深めてほしいと、(公財)日本城郭協会が制定。日付は「し(4)ろ(6)」(城)と読む語呂合わせから。 |
| 新聞をヨム日 | 入社・入学などで新しい生活をスタートする若者に新聞の購読を呼び掛けようと、(一社)日本新聞協会の販売委員会が制定。日付は「よ(4)む(6)」(読む)と読む語呂合わせから。 |
| 養老渓谷の日 | 千葉県有数の温泉地であり、市原市の観光スポットである養老渓谷の名を広め、多くの人にその魅力を楽しんでもらいたいと、(一社)市原市観光協会が制定。日付は「よう(4)ろう(6)」(養老)と読む語呂合わせから。 |
本日の誕生日
4月6日には、ルネ・ラリック(ガラス工芸家)、桂米丸(落語家)、アート・テイラー(ジャズミュージシャン)、小沢昭一(俳優)、アントン・ヘーシンク(プロレス)、田嶋陽子(女性学研究家)、伊東ゆかり(歌手)、長戸大幸(音楽プロデューサー)、玉木正之(スポーツライター)、ジャネット・リン(フィギュアスケート)、宇津木妙子(ソフトボール)、秋山幸二(プロ野球)、谷川浩司(将棋棋士)、サラ・カサノバ(日本マクドナルド会長)、宮沢りえ(女優)、キャンディス・キャメロン・ブレ(女優)、乙武洋匡(スポーツライター)が誕生しています。(敬称:略)