【要約】【日経の大嘘】長期金利上昇!財政悪化への懸念で【髙橋洋一チャンネル#1398】
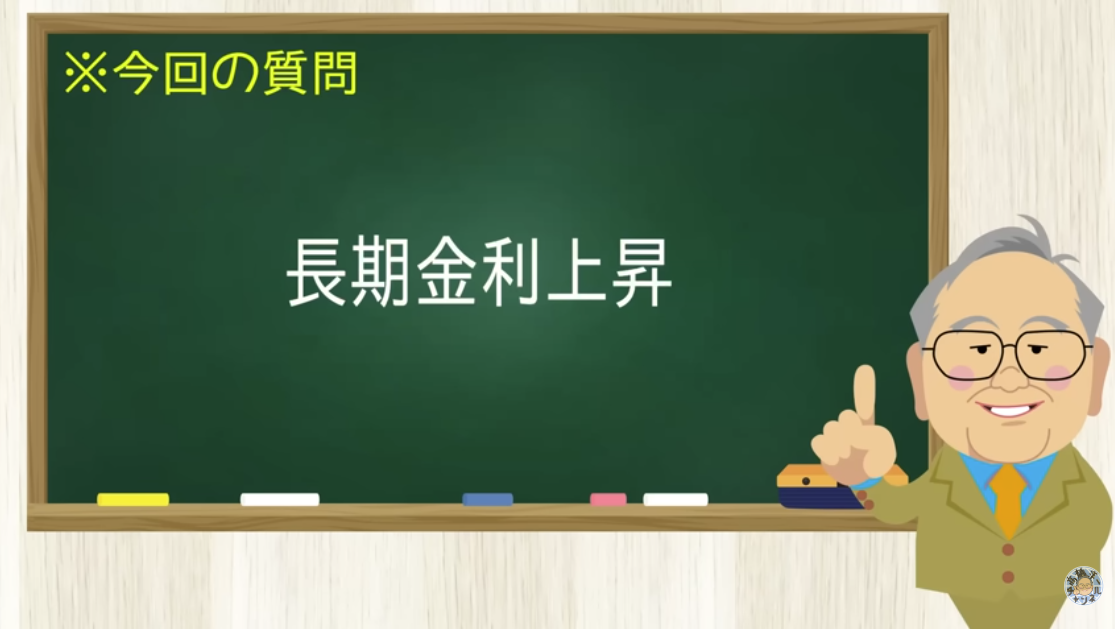
INDEX(目次)
- 長期金利上昇
- 『高橋洋一チャンネル#1398』の内容を要約
- 日経「長期金利1.75%上昇=財政懸念」への違和感
- 高市政権の投資・成長期待が金利に及ぼす影響
- 名目成長率と名目長期金利は“だいたい同じ水準”に落ち着く
- 今の日本は名目成長率がやや高め→金利上昇は自然
- 名目成長率が上がると金利が上がる理由(所得と負担の関係)
- 景気と金利の単純な循環
- 「金利上昇で大変だ」と騒ぐ風潮への批判
- 日銀の金融政策と長期金利のつながり
- 庶民の住宅ローンはどうなるか?
- 「財政が悪いから金利が上がる」論のズレ
- 日経の“意図”への指摘(積極財政叩きの道具)
- 「財政リスクを反映しやすい長期金利」も誤り
- CDSで見る“日本の財政破綻リスクの低さ”
- 民主党政権時代のCDS急騰が示すもの
- 「数字は嘘をつかない」結論
長期金利上昇
『高橋洋一チャンネル#1398』の内容を要約
日経「長期金利1.75%上昇=財政懸念」への違和感
・11月18日の日経は「長期金利が1.75%に上昇、財政への懸念続く」と報道
・しかし「長期金利上昇→財政悪化が原因」と直結させるのは根拠が薄い
・日経は“財政のせいで上がった”と決めつける書き方だが、理論的には別の説明が自然
高市政権の投資・成長期待が金利に及ぼす影響
・高市政権が新規投資を増やす方向なら、経済の成長率(期待成長率)が上がる可能性がある
・期待成長率が上がれば、金利が上がるのは普通の経済メカニズム
・「金利上昇=悪いこと・財政不安」という短絡は、成長局面の基本を無視している
名目成長率と名目長期金利は“だいたい同じ水準”に落ち着く
・ざっくり言うと、名目経済成長率と名目長期金利は長期的に近い水準になりやすい
・この関係があるため、長期金利が上がること自体は“財政問題の証拠”ではない
・理論を知っている人なら「成長期待が上がったので金利が上がる」で済む話
今の日本は名目成長率がやや高め→金利上昇は自然
・現在の日本は名目成長率が少し高い状態
・だから長期金利がもう少し上がっても不思議ではない
・仮に上がったとしても「だから何が致命的なのか?」という程度の変化にすぎない
名目成長率が上がると金利が上がる理由(所得と負担の関係)
・名目成長率が上がる=物価や所得が上がる局面
・所得が増える見通しがあるなら、多少金利が高くても返済負担に耐えられる
・逆に所得が上がらないのに金利だけ高いと、借り手が減って景気のブレーキになる
・そのため、経済は「成長率と金利が極端に乖離しない方向」に自動的に動く
景気と金利の単純な循環
・景気が良くなると投資や住宅購入など“借りたい人”が増える
・借りたい人が増えれば金利は上がる
・しかし金利が上がりすぎると、借りた後の収益が見合わなくなり借り手が減る
・借り手が減ると金利は下がる・落ち着く
・つまり金利は景気とセットで上下する「普通の現象」
「金利上昇で大変だ」と騒ぐ風潮への批判
・世の中には金利が少し動くだけで「大変だ」と言う人が多い
・そのくらいの変化が予測できない人が語っているのでは、と皮肉
・金利の上昇局面は“成長や所得上昇の裏側”であることが抜け落ちている
日銀の金融政策と長期金利のつながり
・成長率が上がればインフレ率も高まりやすい
・インフレ率が高まると日銀は引き締め方向になり、政策金利(短期金利)が上がると市場が予想する
・長期金利は「将来の短期金利予想の平均値」で決まる
・将来の短期金利が上がると思われれば、長期金利も上がる
・よって今回の長期金利上昇も“正常な期待の反映”として説明できる
庶民の住宅ローンはどうなるか?
・短期的にはローン金利上昇が“ちょっと大変”に見える局面もある
・ただし成長・所得が一緒に上がっているなら、長い目で見ると負担は吸収されやすい
・経済はそういう形でバランスするので、一方的に悲観するのは誤り
「財政が悪いから金利が上がる」論のズレ
・金利上昇を財政だけで語るのは何度も繰り返されるミス
・政府は負債だけでなく資産(金融資産など)も大量に持つ
・金利が上がっても、資産の利回りも上がるため政府全体でみれば致命的ではない
・本当に困るのは「資産がなく負債だけ持つ人」
・しかし現実には借金の裏に何らかの資産(住宅・不動産・設備など)があるのが普通
・資産価値も名目成長と一緒に上がりやすいので、金利だけを見て騒ぐのは片手落ち
日経の“意図”への指摘(積極財政叩きの道具)
・日経は「責任ある積極財政を支持する議員連盟が25兆円規模を要求→消しからん」という文脈で書きたい
・その“消しからん論”を補強するために金利上昇を持ち出している
・記事の狙いは「財政を出すのは悪い」と言うための材料集めに見える
「財政リスクを反映しやすい長期金利」も誤り
・長期金利は短期金利より高いのが普通で、上昇すること自体が自然
・そこに「財政リスクが反映された」と特別視するのは勘違い
・長期金利の動きは成長・インフレ・金融政策期待から説明できる
CDSで見る“日本の財政破綻リスクの低さ”
・提示した図は5年物CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)
・CDSは日本国債を買ったときの“保険料”で、日本の信用リスクが市場で値付けされる指標
・CDSから財政破綻確率を推計でき、現在は0.3%程度など極めて低い水準
・G7の中でも信用度は上位(2〜3位あたり)で安定している
民主党政権時代のCDS急騰が示すもの
・民主党政権の頃はCDSが“べらぼうに高い”=市場が強い財政不安を抱いていた
・政権交代が明らかになった時点からCDSが急低下しており、市場は政策の期待に正直に反応
・当時は「事業仕分けで緊縮のイメージ」だったが、実際は経済運営が下手で信用を悪化させた
・東日本大震災対応の失敗や復興増税も大きなマイナスだったと指摘
「数字は嘘をつかない」結論
・人の言説は嘘をつくことがあるが、数字は現実を示す
・CDSの推移を見れば、民主党時代の政策は市場に否定され、アベノミクス以降で改善してきたのが一目瞭然
・今の局面で「財政懸念で金利が上がった」と騒ぐより、データに基づき冷静に見るべき
キーワード:長期金利,1.75%,日経新聞,財政懸念,高市政権,新規投資,期待成長率,名目成長率,名目長期金利,金利と成長の関係,所得増,借り手と金利循環,日銀金融政策,政策金利,短期金利予想,インフレ率,住宅ローン,政府の資産と負債,積極財政25兆円,ミスリード批判,財政リスク論,5年CDS,日本の信用度,財政破綻確率,民主党政権,事業仕分け,復興増税,アベノミクス,数字は嘘をつかない

