【要約】高市総理「拉致問題解決に手段を選ばない!」【髙橋洋一チャンネル#1385】
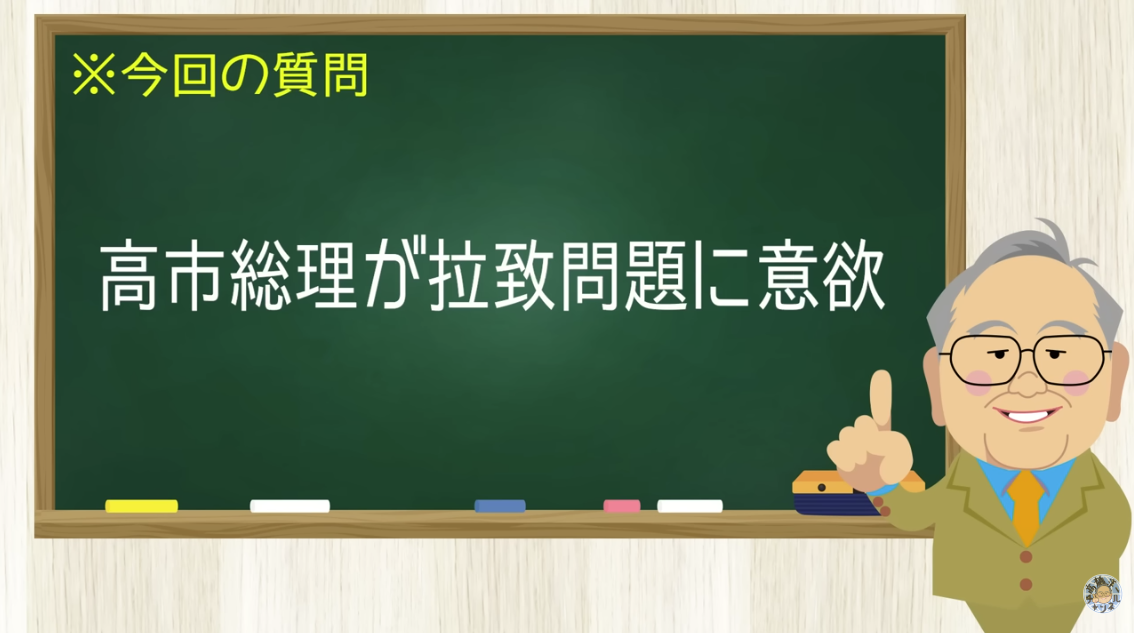
『髙橋洋一チャンネル」は、数量政策学者で嘉悦大学教授の髙橋洋一さんが視聴者の質問に答える形で、政治経済や世界情勢など現在進行中の問題について理路整然と解説してくれるYouTubeチャンネルです。
INDEX(目次)
高市総理が拉致問題に意欲
『高橋洋一チャンネル』の内容を要約
① 高市首相の発言の場と経緯
・高市首相は「全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会」に出席し、非常にタイトなスケジュールを縫って登壇した
・この国民大集会は毎年開かれ、多くの関係者や支援者が集まる、拉致問題では最も重い位置づけのイベントの一つとなっている
・高市首相はここで、従来の「全力で取り組む」という表現を超え、「手段を選ぶつもりはない」と踏み込んだ言葉を用い、会場に強いインパクトを与えた
・発言内容は高橋氏自身もポスト(SNS)で紹介するほど注目度が高く、「本当にそこまで言ったのか」と周囲を驚かせるレベルだった
・これにより、高市首相がこの問題を政権の最重要課題の一つとして位置づけていることが、改めて内外に示された
② 「手段を選ぶつもりはない」発言の意味と受け止め
・「手段を選ぶつもりはない」という言葉は、人によっては自衛隊による救出作戦や、北朝鮮領内への直接行動まで連想させるほど強いニュアンスを持つ
・一部には「自衛隊を送り込むつもりなのか」と解釈する向きもあり、それだけ発言が生々しく、従来の政治家の表現とは一線を画すものだった
・ただし文脈としては、「自分自身が先頭に立ち、必要であれば北朝鮮まででも出向く覚悟で取り組む」という、政治トップとしての決意表明とみるのが妥当とされる
・これまで「高市首相は拉致問題に弱いのではないか」という批判やイメージも一部にあったが、今回の発言はむしろその評価を覆す内容だと高橋氏は指摘している
・高市首相はもともと政策全般で「エネルギー120%」型の政治家と評されており、拉致問題でも妥協なく突き進む姿勢を示したと受け止められている
③ トランプ前大統領をテコにした外交戦略の継承
・高橋氏は、安倍元首相がトランプ前大統領との強固な個人的関係をテコに、北朝鮮問題の打開を試みていたことを振り返る
・トランプが来日した際には、ルビオ議員らの協力も得ながら拉致被害者家族とトランプを会わせ、問題を強く印象づけようとした経緯がある
・安倍政権時代は、「日本だけでは北朝鮮を動かすのは難しい」という前提のもと、トランプを通じて金正恩に圧力・交渉をかけるルート構築が狙われていた
・最終的に拉致問題の大きな進展には至らなかったものの、「かなりギリギリまで詰めていた」と高橋氏は評価し、北朝鮮側の事情で頓挫した側面が大きいと見る
・高市首相はこうした経緯をよく見てきた立場にあり、再びトランプが米政権に戻れば、同様にトランプを「てこ」とする戦略を取れると計算している可能性がある
・北朝鮮と会談できる可能性が最も高いのはトランプだという前提に立ち、高市首相も「トランプとの強い連携」を念頭に置いた外交カードを構想していると考えられる
④ 北朝鮮・ロシア・中国の結束で難しくなった国際環境
・第1次トランプ政権当時、北朝鮮はロシア・中国との距離をやや置きつつ、アメリカとの直接交渉に活路を見出そうとしていた面があり、米朝首脳会談が実現した
・しかし現在は、ロシア・中国・北朝鮮の3カ国が、北京の軍事パレードで並んで写真撮影するほど、対米・対西側を意識した「準同盟関係」に近づいている
・この三角関係が固まる中で、日本が北朝鮮だけを1枚「はがす」ことは、以前よりはるかに困難になっており、従来の圧力と対話の枠組みも機能しづらい
・北朝鮮は米本土に届くとされるミサイルも保有し、軍事力を着実に増強しており、一方的に追い詰められている弱い立場ではなくなりつつある
・経済制裁などで内部的には厳しさもあるとみられるが、「体制崩壊の危機」という感覚まではなく、むしろ核・ミサイル戦力による抑止をテコに交渉力を高めている
・こうした状況下で日本が拉致問題だけを単独で動かそうとしても、国際情勢の制約が大きく、「外交的に極めて苦しい局面」にあると高橋氏は分析している
⑤ 小泉訪朝・ブッシュ政権期との比較と、交渉が難しくなった理由
・小泉元首相が訪朝し、一部拉致被害者の帰国を実現した当時は、アメリカではブッシュ政権が北朝鮮を「悪の枢軸」と名指しし、他の国に対しては実際に軍事行動をとっていた
・北朝鮮側には「次は自分たちが攻撃されるかもしれない」という強い恐怖感が生まれ、その「隙」を日本側が利用して一気に交渉を進めたのが小泉訪朝の背景だと説明される
・ブッシュ政権の圧力と、日本側の働きかけが巧みに噛み合ったタイミングであり、現在の状況と比べると、北朝鮮を交渉のテーブルに引き出しやすい環境だった
・一方で、オバマ政権以降、特にバイデン政権期は北朝鮮問題が停滞し、日本側も岸田政権~石破政権にかけて対北外交が事実上あまり動かなかったとされる
・その間に北朝鮮は中国・ロシアとの関係を一層強化しながら核・ミサイル開発を進め、日本や米国が手を打ちにくい「既成事実」を積み重ねてしまった
・結果として、現在は小泉訪朝やトランプ・金正恩会談の頃よりも、はるかに外交的な選択肢が限られ、「苦しいが、それでもボールを投げ続けるしかない局面」にあるという整理がなされている
⑥ 軍事的奪還の非現実性と、外交カードを「打ち続ける」しかない現実
・アメリカの場合、過去に特殊部隊を使って人質救出を行った例があり、十分な情報さえあれば「直接取り返しに行く」作戦を選択することもあり得る
・しかし北朝鮮は情報が極端に取りづらく、日本側が「拉致被害者がどこにいるか」を特定することすら難しいため、同様の軍事作戦は現実的ではないと高橋氏は見る
・日本の憲法・法制度、自衛隊の位置づけ、日米同盟の枠組みなどを考え合わせると、日本単独での武力奪還はほぼ不可能であり、選択肢は外交・経済的圧力と交渉に限定される
・こうした厳しい制約のもとで「手段を選ぶつもりはない」と言うのは、物理的な武力行使というより、「考え得るあらゆる外交カードを投げ続ける」という比喩と捉えるべきだという解釈が示されている
・高市首相は、国際情勢や米政権の動向を見ながら、トランプとの連携、国際世論の喚起、制裁・支援の組み合わせなど、使えるカードを「弾をたくさん投げる」ように次々と試す覚悟を表明したと総括される
キーワード:高市首相,拉致問題,手段を選ぶつもりはない,全拉致被害者即時一括帰国,国民大集会,自衛隊派遣との連想,トランプ前大統領,安倍元首相,日米連携,ロシア・中国・北朝鮮,小泉訪朝,ブッシュ政権,悪の枢軸,特殊部隊,共和党政権,対北外交の行き詰まり,外交カード,軍事的奪還の非現実性

