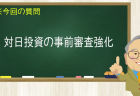【要約】遂にトランプに泣きついた“追い詰められた中国”【門田隆将チャンネル#0047】

遂にトランプに泣きついた“追い詰められた中国”
『門田隆将チャンネル#0047』を要約
習近平がトランプに“泣きつき” 日本が動かないことへの中国の焦り
・門田氏は「日本が動かなければ中国は大変なことになる」と繰り返し指摘してきたと説明
・中国の焦りの背景には、台湾侵攻を実行に移したいという習近平側の思惑があると分析
・そのため、中国と歩調を合わせる日本国内の勢力=「うちなる敵」が、高一首相の発言を撤回させようと総攻撃を仕掛けていると批判
・「収束を望むが情報を引き出せない中国の焦り」という前回テーマの延長線上で、ついに習近平がトランプに電話をかけるところまで追い詰められたと強調
日本の「うちなる敵」と台湾侵攻を呼び込む言論
・門田氏が「うちなる敵」と呼ぶのは、朝日新聞・毎日新聞・NHKなどのオールドメディアや、岡田克也氏を中心とした野党勢力
・これらは習近平の側に立ち、高一首相の台湾関連発言を撤回させようと一斉に攻撃していると指摘
・その狙いは、中国が台湾に侵攻しやすい環境を整えることであり、日本の安全と世界の平和、自国民の命を危険にさらしていると批難
・官邸前デモに参加した福島瑞穂氏が、中国中央電視台(CCTV)のインタビューに応じ、「日本国民は高一首相に怒っている」とアピールしていることも「うちなる敵」の典型例として紹介
安倍外交との違いと中国ロビーの“ルート消滅”
・安倍政権の7年8カ月も「世界の中心で咲く日本外交」という意味では優れていたが、当時は自民党幹事長・二階俊博氏を通じて中国が様々な働きかけを行えていたと指摘
・一方、現在の幹事長は鈴木俊一氏、官房長官は木原氏であり、中国側が従来のように使える“ルート”がないと解説
・その結果、中国は日本政府への直接ロビーに苦しみ、門田氏が「中国の焦り」として指摘してきた動きが加速
・ついにはアメリカにまで“泣きつき”、トランプ大統領との電話会談に活路を求めるに至ったと語る
米中電話会談の内容と歴史認識の問題
・ブルームバーグは14時半に、前日に習近平がトランプ大統領に電話したと報道
・その後、高一首相はトランプ大統領の要請で急遽電話会談を実施し、会談後の官邸で、トランプ氏から最近の米中関係と習近平との電話内容について説明があったと記者団に語った
・読売新聞によれば、習近平は「中国とアメリカはかつて共にファシズムや軍国主義と戦った」「第二次世界大戦の勝利の成果を守るためにも協力すべきだ」と発言したとされる
・門田氏は「80年前、中華人民共和国は存在せず、中華民国の話である」と指摘し、歴史を都合よく利用して台湾問題での自らの主張を正当化し、日本を牽制していると批判
高一首相の対中姿勢と過去政権との決定的な違い
・G20などの国際会議で、高一首相は中国の李強首相が近くにいても一切近づかず、過去の政権とは全く異なる姿勢を示していると評価
・野田佳彦元首相が尖閣問題で中国に強く出られた際、慌てて駆け寄るような「惨めな姿」を晒したことと対比
・中国側は様々なルートを使って高一首相の発言撤回を迫ったが、首相は応じず、「ここで譲れば終わり」という覚悟で一切受け付けなかったと説明
・中国は国連事務総長宛てに「高一がこういうことを言っている。確認してほしい」と訴えるなど、国際機関も巻き込んだ工作を展開
中国がアメリカまで使おうとする異常さと「うちなる敵」の動揺
・習近平がトランプ大統領にまで直接電話し、台湾問題での発言撤回を引き出そうとしたことに、門田氏自身も「さすがに予想外」と驚きを示す
・しかし、トランプ大統領が「俺に台湾に侵攻させよう」という要求を飲む理由はなく、世界が納得するはずもないと断じる
・一方、日本国内では“うちなる敵”が動揺し、高一政権を崩したいが、支持率の高さと国民世論がそれを許さない構図になっていると解説
世論調査が示す高一政権支持と台湾答弁への評価
・産経・FNN合同世論調査で高一内閣支持率は75.2%、読売・NNN調査でも72%台と非常に高水準
・産経新聞一面によると、高一首相の台湾関連答弁を「適切」と評価する人は61%に達し、国民はオールドメディアよりはるかに賢明だと門田氏は評価
・毎日新聞は、外国人による土地取得や在留資格見直しについて「排外主義を助長するとの批判もある」と前置きした上で、高一首相の方針を評価するかと質問
・誘導的な聞き方にもかかわらず「評価する」が71%となり、世論誘導に失敗
・台湾有事に関する答弁について「問題があったと思うか」との設問でも、「問題があった」が25%にとどまり、「問題があったとは思わない」が50%と多数
・門田氏は、左翼・媚中派がどれだけ中国寄りの質問を繰り返しても、国民は本質を理解しており、高一首相の姿勢を支持していると強調
「琉球有事は中国有事」 中国の沖縄・日本への長期的な侵略工作
・中国のSNS上では「琉球有事は中国有事」というスローガンが拡散し、「台湾は日本有事」という日本側のロジックへの“痛烈な皮肉”だと宣伝されていると紹介
・中国側は「日本は中国の属国だった琉球を武力で奪った」「ポツダム宣言では琉球の地位は未確定」といった主張を展開し、琉球=沖縄を中国領とする世論を喚起
・門田氏は、自身の著書『日中友好侵略史』で示したように、中国は長年「琉球特別自治区準備委員会」などの組織を立ち上げ、2010年・2012年から「琉球は中国」「中華民族琉球特別自治区」といった広告を各紙に出してきたと説明
・2012年の広告には、「大和民族は中華民族の一部分、日本は中華の血脈」と明記されており、「沖縄の次は日本全体を取る」という本音が示されていると指摘
・2016年には、中国紙が「琉球諸島の地位は未定、日本の沖縄と呼んではならない」とする論評を掲載し、一貫して沖縄の主権を揺さぶる情報戦を展開
玉城デニー知事当選と中国メディアの“沖縄利用”
・玉城デニー氏が沖縄県知事選に勝利した2022年、中国メディアは「沖縄県民の正義の訴えが再び無視されてはならない」とする論評を掲載
・その中で「日本の米軍基地の70%が沖縄に集中」「女子学生暴行事件」などを取り上げ、沖縄の米軍基地を「毒の源」と位置づけ、撤去を煽る論調を展開
・門田氏は、これは「米軍を沖縄から追い出す」中国側の長期的工作の一環であり、沖縄世論を利用しつつ、日米同盟の弱体化を狙っていると分析
日米同盟・抑止力と高一首相の台湾答弁の意味
・もし高一首相が、岡田氏の質問に押されて「米国が攻撃されても存立危機事態にはなりえない」と答えていたら、アメリカは「日本は助ける気がない」と判断し、沖縄から軍を撤退させる可能性が高いと警告
・米軍がグアムなどへ引き上げれば、沖縄は一気に中国の勢力圏に組み込まれていく危険があると指摘
・今回の高一首相の答弁は、沖縄と台湾を守るための抑止力維持に直結しており、「絶対に譲ってはならない一線」を守ったものだと高く評価
・中国側の本当の狙いは「米軍、沖縄から出て行け」というものであり、日本の「うちなる敵」もそれに呼応して世論操作を試みたが、国民は賢明にそれを見抜いていると述べる
中国の対日工作が通じない“戦後初”の政権と今後への期待
・門田氏は、1972年の日中国交正常化以前、佐藤栄作首相までは中国が日本政治を大きく揺さぶる力を持っていなかったと回顧
・田中角栄内閣以降、中国は長年、日本政権に影響力を行使しようとしてきたが、高一政権は“中国の言うことに左右されない初めての政権”だと位置づけ
・安倍政権の7年8カ月ですら、二階氏の存在などにより中国の工作は完全には途絶えなかったが、高一政権にはその「ルート」が見当たらないと指摘
・ヨハネスブルクの国際会議でも高一首相は一歩も歩み寄らず、中国側は「この政権が長期化すれば経済的にも大変なことになる」と危機感を募らせていると分析
・その結果、中国は焦りから次々と失敗を重ね、アメリカへの“泣きつき”という異例の行動にも出ていると総括
視聴者への呼びかけと締めくくり
・門田氏は、外務省内の「チャイナスクール」による情報取引にも目を光らせつつ、中国の焦りに伴う多様な工作に警戒が必要だと訴える
・高一首相には、アメリカからの圧力や工作が仮にあったとしても、決してぶれてはならないと念押し
・視聴者に対し、「高一さんを支え、背中を押し、先人たちが守ってきた日本を共に守り抜こう」と呼びかけて動画を締めくくった
キーワード:習近平,トランプ大統領,台湾侵攻,高一首相,台湾答弁,内閣支持率,世論調査,うちなる敵,朝日新聞,毎日新聞,NHK,国連事務総長,琉球有事,琉球特別自治区,沖縄,米軍基地,日米同盟,存立危機事態,チャイナスクール,対中工作,抑止力,安倍外交,二階俊博,玉城デニー