【要約】中国が敵国条項を持ち出した。アナタ死文化に賛成してますけど?【髙橋洋一チャンネル#1402】
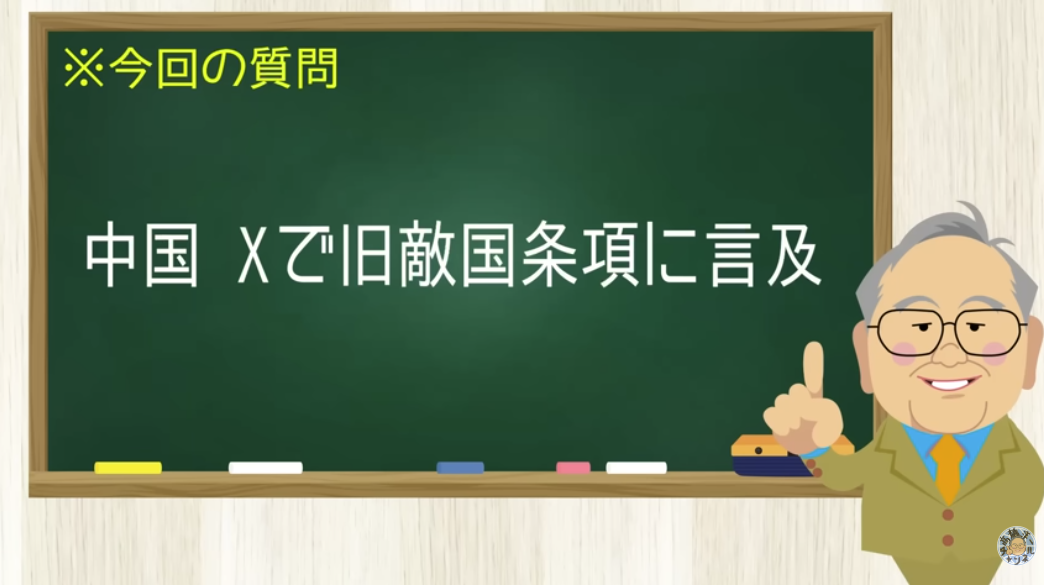
INDEX(目次)
中国 Xで旧敵国条項に言及
『高橋洋一チャンネル#1402』の内容を要約
中国の「敵国条項」持ち出し発言とその無効性
・11月21日付の日経新聞によると、中国の日本大使館が「国連の許可なしに日本を軍事攻撃できる国際法上の権利がある」と主張し、国連憲章の旧敵国条項に言及
・中国側は、日本など旧枢軸国に対しては安保理の許可なしに軍事行動が可能だとする解釈を示し、日本側に強い違和感を与えた
・しかし旧敵国条項は、1995年の国連総会決議で「すでに時代遅れ(私分化)と認識された規定」として圧倒的多数で確認済み
・2005年の国連首脳会合でも、国連憲章から同条項を削除する方向性を示す決議が採択されており、中国自身もこれらの決議に賛成している
・つまり、中国は過去に「敵国条項は実質無効」とする流れに賛成しておきながら、今になって都合よく持ち出しているという自己矛盾を抱えている
外務省の対応と「ウィットの効いた反論」の必要性
・高橋氏は、旧敵国条項が私分化しているという国際的コンセンサスを、外務省はもっと自信を持って示すべきだと指摘
・本来なら、「中国様が2回も決議に賛成してくださったおかげで、旧敵国条項の私分化が順調に進みました。誠にありがとうございます」と、皮肉を込めて返すくらいの余裕が必要だと提案
・日本政府は形式的・お役所言葉のコメントにとどまらず、SNSなどでユーモアも交えた発信をすれば、国際世論にも分かりやすくアピールできたはずだと批判
・日本国内でも、かつて一部政党が中国と同じような「敵国条項」を根拠にした主張をしていたことがあり、高橋氏は「もう少し勉強すべきだ」と嘆いている
中国の嫌がらせ外交と台湾侵攻の行き詰まり
・中国が今さら旧敵国条項を持ち出して日本を威嚇するのは、実質的な打ち手が減り、嫌がらせ的な手段に頼り始めているサインだと分析
・背景には、「日本が自衛隊を通じて米軍を支援すれば、中国の台湾侵攻作戦は成立しない」という現実が、中国側にとって大きなネックになっているとの見方
・短期的な外交の駆け引きだけを見ると、中国の強硬姿勢が目立つが、本質的には台湾有事のシミュレーションがうまくいかない焦りが根底にあると指摘
日米・日中首脳会談、高市首相の発信と習近平の怒り
・先日の日米首脳会談の後、当初予定に無かった日中首脳会談が北京で設定され、日本側の有能な大使館スタッフが段取りをつけたと言われている
・しかしその直後、高市首相は台湾とも会談し、対中警戒や安全保障に関する本音を次々と発信したため、それを知った習近平国家主席が驚き、激怒したという見方がある
・習氏は「事前に用意した台本通りに進まないと怒るタイプ」と評される一方、高市首相はほとんど原稿を用意せず即興で発言するため、相手側からは動きが読みづらい
・高橋氏は、この「予測不能さ」はトランプ元大統領にも通じるスタイルであり、中国側は従来型の対日外交の延長線上では対応しきれていないと分析
短期的な対立と長期的構造要因の二重構造
・日中首脳会談では高市首相がかなり踏み込んだ発言をしたにもかかわらず、中国は表向き会談を評価するコメントを出した
・これは、会談実施を事前に決めてしまったため、あとから「評価しない」とは言いにくく、形だけ評価コメントを出した結果だとみられる
・その一方で、「なぜあんな会談をやったのか」と党内で怒りが噴出している可能性もあり、短期的には感情的な反発が強まっている
・しかし長期的に見ると、やはり鍵は台湾侵攻の困難さであり、中国は日本と米軍が連携した場合、自らの戦略が破綻することを意識せざるを得ない状況に追い込まれている
・準備不足のまま高市政権の出方を見ながら対応しているため、一手一手が裏目に出て自縄自縛になっていると高橋氏は指摘
G20の混乱、イスラエル問題と高市外交の選択
・今回のG20は、シンガポール経由で南アフリカに向かう「1泊4日」の過密日程で、高市首相にとっても極めて厳しいスケジュールだった
・中国との直接会談を見送ったのは、どうせ習近平側から「発言を撤回しろ」と言われるだけで建設的な議論にならないと判断した可能性が高いと分析
・会議が始まった直後に共同宣言を採択するなど、プロセスも実質的な議論を経たものとは言い難く、その場に高市首相がいなかったこともあり「コンセンサスなき共同宣言」と評される
・トランプ元大統領が参加していなかったほか、アルゼンチン大統領は公然と共同宣言に反対を表明するなど、G20はもはや「一枚岩のフォーラム」とは言えない状態
・特にイスラエルをめぐるスタンスで、南アフリカやトルコなどは強い反イスラエル、アルゼンチン・アメリカ・インドなどは比較的親イスラエル寄りと立場が分裂
・そのため、高市首相としてもG20そのものを過度に重視せず、むしろ個別の首脳との会談や二国間関係の強化に力点を置いているとみられる
女性首相ならではの「握手外交」と顔を売る戦略
・高市首相は、イタリアのメローニ首相との抱擁など、女性同士だからこそ可能な距離感の近いボディランゲージを通じて存在感を示している
・日本の男性首相では難しい「ハグ外交」を自然にこなし、相手との心理的距離を一気に縮めている点を高橋氏は高く評価
・G20などの国際会議では、事前に「どの場で誰と握手するか」のリストを作り、それを頼りに会場を回って各国首脳と積極的に握手・挨拶して回っているとのエピソードも紹介
・その場で長く話し込むことよりも、「顔と名前を覚えてもらうこと」を優先し、初の日本人女性首相としての注目度を最大限に活かした“顔売り外交”を展開
・こうした地道な握手外交が、今後の首脳会談の敷居を下げ、日本の発言力強化にもつながると見られている
キーワード:敵国条項, 私分化, 国連総会決議, 中国大使館声明, 外務省の対応, 嫌がらせ外交, 台湾侵攻抑止, 日米首脳会談, 日中首脳会談, 高市首相, 習近平の怒り, G20共同宣言, イスラエル問題, メローニ首相, 握手外交, 女性首相, 顔を売る戦略

