【要約】ノーベル賞受賞も金が無い!高市さんになってドンと研究費を!【髙橋洋一チャンネル#1372】
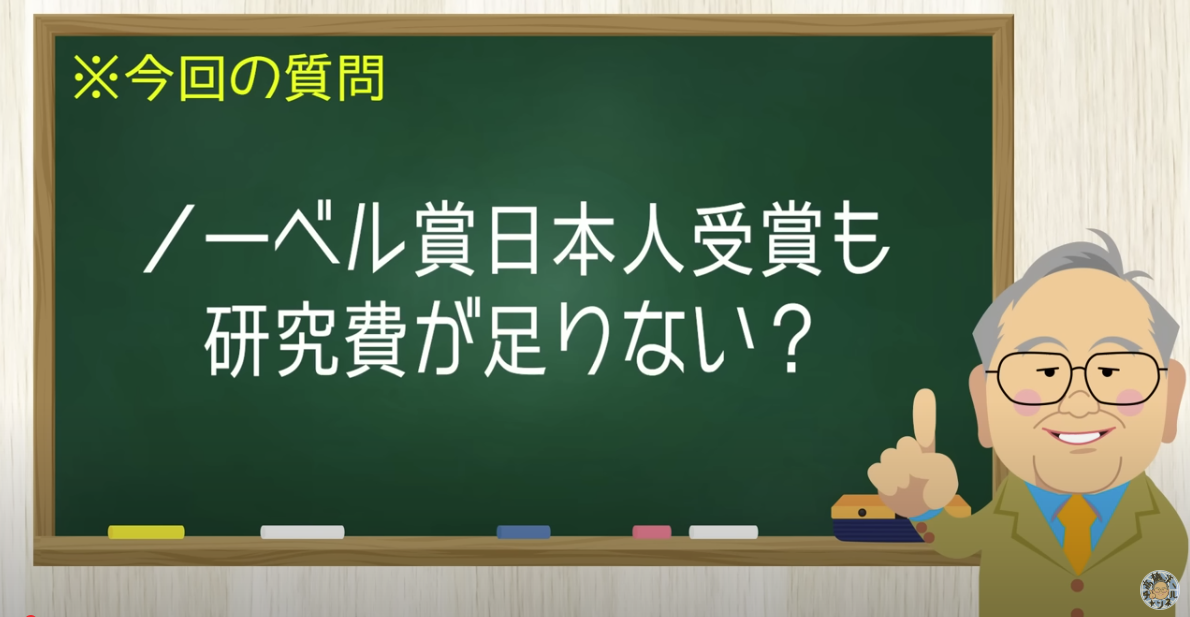
『髙橋洋一チャンネル」は、数量政策学者で嘉悦大学教授の髙橋洋一さんが視聴者の質問に答える形で、政治経済や世界情勢など現在進行中の問題について理路整然と解説してくれるYouTubeチャンネルです。
INDEX(目次)
ノーベル賞日本人受賞も研究費が足りない?
『高橋洋一チャンネル』の内容を要約
坂口志文氏 ノーベル医学・生理学賞受賞と「基礎研究費不足」への訴え
・ノーベル生理学・医学賞に大阪大学特任教授の坂口志文氏が選ばれた。受賞会見で坂口氏は「今後は基礎研究への支援をお願いしたい」と述べ、日本の研究費不足を訴えた。
・日本の研究現場では、欧米諸国に比べて基礎研究資金が半分程度しかなく、優秀な研究者ほど資金調達に苦労している現状がある。
・高橋氏は「この問題は以前から分かっていた」と指摘し、安倍政権時代に基礎研究支援のため設けられた「10兆円ファンド」が本来の趣旨どおり機能していないと批判した。
10兆円ファンドの仕組みと運用問題
・10兆円ファンドは、もともと国が国債を発行して資金を作り、それを基礎研究に回すための基金として設計された。
・高橋氏によると、当初は「元本を切り崩して直接研究資金として支出する」仕組み(=切り崩し型ファンド)を想定していた。
・しかし財務省と文部科学省が途中で制度を変更し、「10兆円はそのまま残し、運用益だけを配分する運用型ファンド」にしたため、実際に研究現場に届く資金はごくわずかになった。
・この「運用益配分型」は安全重視だが、利回りが小さいため年間に使える額も小規模となり、研究支援の効果が限定的になっている。
・高橋氏は「元本を切り崩して使っても財政的に問題ない」「10兆円など国の財政規模から見れば微々たるもの」と主張。国債を発行し直せば再び資金を確保できると述べた。
「切り崩し型」への転換提案と財務省への批判
・高橋氏は、研究への直接支援を増やすためには「切り崩し型」に戻すことが最も効果的だと指摘した。
・「国債を発行して10兆円の基金を作り、それをどんどん使っても将来の研究成果で十分に回収できる。借金を怖がる必要はない」と述べた。
・財務省や文科省が「10兆円は大切に残すべき」として支出を渋っている現状について、「お金の使い方を分かっていない」「非常にちまちました発想」と痛烈に批判。
・また、10兆円ファンドの恩恵が東北大学など一部大学に偏っており、大阪大学が十分な支援を受けられていない点にも触れ、「受賞を機に大阪大学も堂々と声を上げてよい」と述べた。
高市政権なら変わる可能性と今後の展望
・高橋氏は「高市早苗氏が首相なら、研究開発投資の重要性を理解しているため、この方針は変わる可能性がある」と述べた。
・高市氏は「基礎研究にこそ公的資金を投じるべき」との立場であり、運用型から切り崩し型への転換を進める可能性が高いと期待を寄せた。
・「仮に10兆円を使い切っても、再び国債を発行してファンドを補充すればよい。重要なのは、今の日本が基礎研究に本気で投資する意思を示すこと」と強調した。
日本が基礎研究に資金をかけなくなった背景
・日本が基礎研究に投資しなくなったのは、およそ25年前、2000年前後の「国立大学法人化」から始まったと高橋氏は説明。
・法人化により、各大学が「自ら資金を集める」ことを求められた一方で、国からの運営交付金が削減され、結果として基礎研究の財源が細った。
・大学が自主的に外部資金を獲得できる体制は整わず、民間や政府の支援も減少。結果として日本の研究環境全体が貧弱化した。
・「このままでは次のノーベル賞が出るまでに20年はかかる」「今回の坂口氏の受賞が最後になるかもしれない」と警鐘を鳴らした。
・基礎研究には長期的な視点が必要であり、国の将来資産として評価すべきと述べ、政府による大胆な財政支援を求めた。
キーワード:坂口志文、ノーベル賞、基礎研究、研究資金不足、10兆円ファンド、運用型ファンド、切り崩し型ファンド、財務省、文科省、高市早苗、国債発行、国立大学法人化、運営交付金削減、日本の科学力低下、研究支援政策

