【要約】新たな暗号資産?ステーブルコインとは一体何か?【髙橋洋一チャンネル#1343】
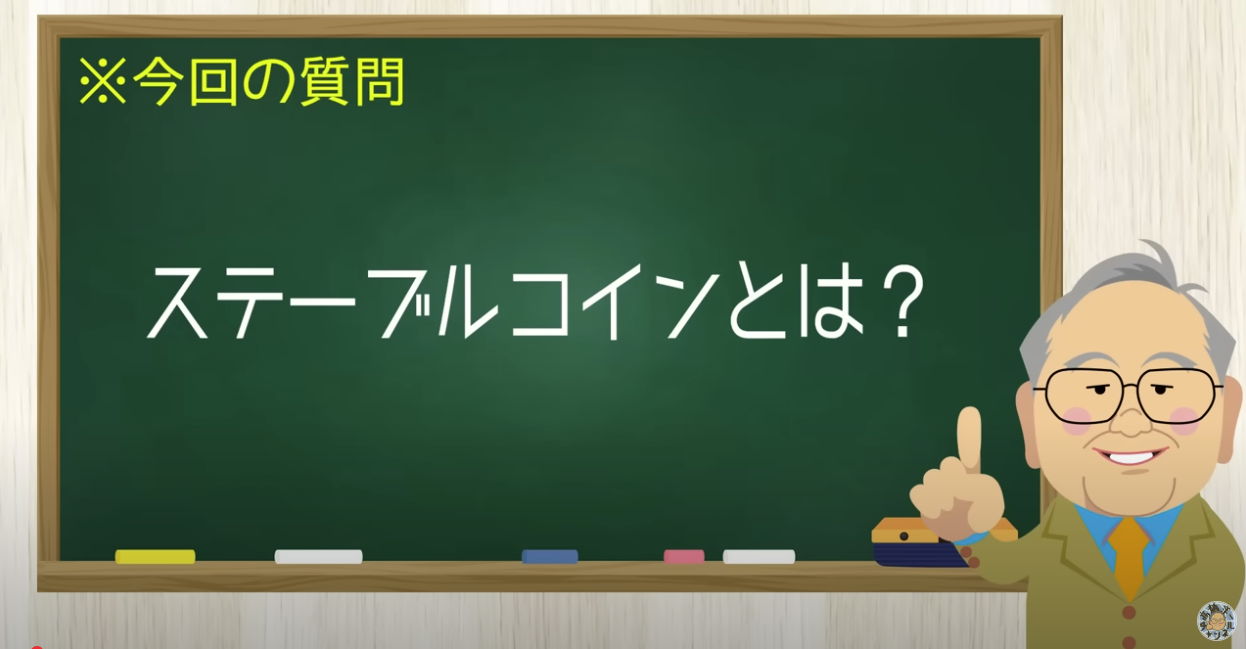
『髙橋洋一チャンネル」は、数量政策学者で嘉悦大学教授の髙橋洋一さんが視聴者の質問に答える形で、政治経済や世界情勢など現在進行中の問題について理路整然と解説してくれるYouTubeチャンネルです。
INDEX(目次)
ステーブルコインとは?
『高橋洋一チャンネル』の内容を要約
国内初の円建てステーブルコイン JPYCが発行へ
・金融庁が承認し、JPYCが秋にも国内初の円建てステーブルコインを発行予定
・従来の暗号資産と異なり「安定した価値」を持つ仕組みで設計されている
ステーブルコインの基本的な仕組み
・発行企業が同額の現金や国債を資産として保有し、その裏付けでコインを発行
・発行企業の会計上では「コイン=負債」「現金・国債=資産」として処理される
・万一の場合でも資産が担保になるため、価格変動が少なく安定性が高い
・従来の暗号資産のような急激な値動きは起こりにくい
銀行との違い
・銀行は「預金」を負債に計上し、それを貸し出して利ざやを稼ぐ「信用創造型」
・一方ステーブルコインは資産をそのまま保有し、決済利用による手数料収入が収益源
・利息は付かず、信用創造機能を持たないため、銀行とは金融システム上の役割が異なる
決済での利用メリット
・国内外の決済や送金に利用可能で、手数料は銀行振込や海外送金より大幅に低い
・小口決済や国際取引でもコストを抑えられるため、利用価値が高い
・発行企業にとっては、決済利用に伴う少額の手数料が主な収益モデルとなる
制度的な位置づけ
・米国などで進む法整備に合わせ、日本でも制度的な枠組みを整備中
・金融庁承認により「安定した決済手段」として公的に認められた
・国際的な取引や金融規制の協調に向けた動きの一環と位置づけられる
中央銀行デジタル通貨(CBDC)との関係
・仕組みとしては、中央銀行が国債を担保に発行する現金に近い構造
・CBDCが発行されればステーブルコインと機能が重複し、民間発行の優位性が低下する可能性あり
・将来的には「民間版デジタル通貨」としてCBDCと共存するか、置き換えられるかが焦点
キーワード:ステーブルコイン、JPYC、金融庁承認、制度的位置づけ、銀行との違い、信用創造、手数料ビジネス、海外送金、安定性、CBDC、中央銀行デジタル通貨

