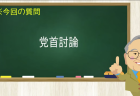【要約】習近平“白旗”、なぜ高市政権の相手は「次々崩れていくのか」【門田隆将チャンネル#0049】

INDEX(目次)
習近平“白旗”、なぜ高市政権の相手は「次々崩れていくのか」
『門田隆将チャンネル#0049』を要約
党首討論と立憲民主党・野田元首相への評価
・前日の党首討論を振り返り、「立憲民主党は日本に必要ないのでは」と感じた視聴者も多かったのではないかと指摘
・野田佳彦元首相は「自分が尖閣国有化で日中関係を悪化させたが、事前にチームを作って準備した」と自己正当化
・それに対して「高市首相は事前準備をしていない」と責めるが、何を言いたいか不明確な質問だと批判
・岡田克也議員の質問は中国の立場を理解し代弁するような内容で、日本の国益に沿わないにもかかわらず、本人に全く反省が見られないと断じる
高市首相の定数削減提案と維新へのメッセージ
・高市首相が討論の中で野田元首相を「野田総理」と呼び、現職総理から元総理へ「定数削減を一緒にやりましょう」と呼びかけた点を高く評価
・2012年当時に安倍総裁(当時)と野田首相が約束した「小選挙区・比例で計45議席削減」が未だ実現していないことを、高市首相は「申し訳ない」と率直に認めた上で、実行を提案
・「小選挙区5減+比例40減」という約束を履行することを、与野党双方の責任として提示し、攻めの姿勢を見せたと解説
・維新が連立条件として「年内に形を示せ」と迫っていた定数削減についても、最大野党に真正面から実現を迫った形で、「どちらが攻めているかは明らか」と評する
習近平がトランプに「台湾で自制」を求めたWSJ報道
・前回動画で取り上げた「トランプに泣きついた追い詰められた中国」について、ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)の記事で具体的中身が明らかになったと説明
・記事によると、習近平はトランプ前大統領との1時間の電話会談の“半分”を台湾をめぐる中国の「歴史的主張」の説明に費やしたと報道
・同時に「世界秩序を守るのは米中両国の共同責任だ」と訴え、高市首相の存立危機事態発言を受けて「トランプはこっちの味方をしてくれ」と告げ口・泣きつきを行った格好だと解説
・その後トランプ氏は高市首相と電話会談し、「台湾の主権に関する話題で中国政府をいたずらに挑発しないように」と助言したとWSJが伝えていると紹介
台湾有事は「第三次世界大戦」という認識
・WSJの記事は、米政府の立場として「台湾に関する中国の主張を承認せず、あくまで『認識』しているに過ぎない」ことを明記しており、番組で繰り返し説明してきた“悪知(acknowledge)”の姿勢と一致すると解説
・米国は台湾に防衛用兵器を供与し、中国が武力で台湾の運命を左右できないよう支援する立場を維持していると説明
・一方、日本の親中派・左派勢力は「台湾侵攻があっても存立危機事態にはならない」「そんな場所に自衛隊を出すのはダメだ」と主張し続けていると批判
・門田氏は以前から「台湾侵攻は第三次世界大戦そのものだ」と訴えており、台湾侵攻を存立危機事態と認めない勢力は、結果的に第三次世界大戦を引き起こす側に加担していると強く非難
トランプ―高市電話会談の裏側(産経新聞報道)
・産経新聞は、トランプ氏から高市首相への電話要請が「25日午前3時」に日本側に伝えられたと詳報し、関係者に緊張が走った様子を描写
・実際の電話会談は、要請から約7時間後に行われ、冒頭は「自分はG20ヨハネスブルクに行かなかったがどうだったか」など雑談から始まったと報じていると紹介
・その上で、台湾を守るという点でトランプ氏と高市首相の認識は一致しており、「挑発はしていないが、あまり挑発と受け取られないよう注意しよう」というニュアンスの会話だったと解説
・門田氏は、高市首相が関西のおばちゃん的な親しみやすさでトランプ氏の心をつかんでおり、相性の良さもあって危うさは感じていないと評価
中国の焦りと「習近平は事実上の白旗」
・門田氏は以前から「中国は焦りに焦ってトランプに泣きついた」と解説してきたが、今回のWSJ報道でその分析が裏付けられたと述べる
・中国は、貿易・経済・台湾問題で収束を望みつつも、自ら有利な情報を引き出せない状態で、危機感からトランプ氏にヘルプを求めた形だと分析
・中国が日本や台湾に経済制裁(例えば水産物輸入停止)などで圧力をかけても、高市首相は動じず、結果として中国側の打つ手が自らを追い詰めていると指摘
・街頭の実感としても、新宿の街を歩くと中国人観光客が減り、かえって歩きやすくなったと述べ、中国側の日本ボイコットが日本にとって致命的打撃になっていない実情を示す
・こうした状況を「習近平は事実上、白旗を上げつつある」と表現し、高市政権の“動じない姿勢”が相手を追い込んでいると強調
公明党・立憲民主党など対中勢力が崩れていく構図
・高市政権発足後、公明党は「高市総理誕生を阻止する」かのように中国の呉江浩駐日大使と直前に会い、その後連立離脱に踏み切った経緯をおさらい
・中国共産党と一体化し、その利益を代弁してきた公明党が与党から去ったことで、中国に配慮して真実を言いにくい構造が一つ崩れたと評価
・立憲民主党も、中国共産党の対外連絡部・統一戦線工作部などと「覚書」を交わしてきた政党であり、そうした過去が高市首相との論戦の中でボロを出し、焦りを露呈していると指摘
・公明党が自ら与党から去り、習近平がトランプに泣きを入れ、立民も中国との関係が足かせになる――こうした流れを、「高市政権に対峙する側が次々と崩れていく構図」として描く
日本の役割と高市政権への期待
・日本は「小さな国」と卑下されがちだが、歴史的にはGDP世界2位を長く維持し、第一次大戦後のパリ講和会議では「人種差別撤廃」を国際連盟規約に盛り込む多数派工作に成功した“大国”であると強調
・自由・民主主義・人権・法の支配という近代民主国家の根本原則をすべて備えた日本が、中国の横暴に対して「武力ではなく理で全面的に対峙する」役割を果たすことを、アジア諸国や自由主義陣営は期待していると説明
・高市首相が掲げた「世界の真ん中で咲き誇る日本外交」は、実際に各国首脳が高市首相と会談したがり、一方で李強首相の方には誰も寄っていかないという対照的な姿にも表れていると指摘
・地上波メディアが依然として高市政権に批判的・歪んだ報道を続けている中でも、国民が高い支持率で高市政権の背中を押し、「動じない日本」を支えることが極めて重要だと訴えかけて締めくくる
キーワード:高市首相,党首討論,立憲民主党,野田佳彦,岡田克也,定数削減,日本維新の会,台湾有事,存立危機事態,習近平,トランプ前大統領,ウォールストリートジャーナル,第三次世界大戦,公明党連立離脱,中国の焦り,日本外交,自由民主主義陣営,人種差別撤廃,日本の大国性