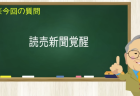【要約】増大する「立憲、許すまじ!」の声。解散・総選挙は不可避【門田隆将チャンネル#0042】

INDEX(目次)
増大する「立憲、許すまじ!」の声。解散・総選挙は不可避
『門田隆将チャンネル#0042』を要約
解散総選挙「不可避」との確信
・前日の動画「中国が急付上させる解散総選挙」が大きな反響を呼び、永田町でも多くの関係者から声を掛けられた
・その流れで「楽待チャンネル」で藤井聡教授と対談したところ、教授も「解散総選挙しかない」と同意
・対談を通じ、筆者自身も「解散総選挙は不可避だ」と改めて確信した
中国の対日圧力と“印象操作”への怒り
・中国が日本の左翼・媚中勢力に“同調を迫る”かのように、2つの圧力を同時に発動したと指摘
・①中国人旅行の「自粛」要請(訪日抑制)
・②日本の水産物輸入の再停止
・読売新聞社説を引用し、中国の対日“悪宣伝”が度を越していると批判
・中国中央テレビが、日中局長協議で「中国側が見下ろし、日本側が頭を下げたように見える場面」を強調して放送
・この映像が中国SNSで拡散され、「中国が優位」と宣伝する悪質な印象操作だと断じる
・高市首相の答弁は台湾「民族」問題ではなく、日本の安全に直結する台湾周辺の武力紛争への見解であり、中国の反発は筋違いと主張
・中国では日本アニメ映画の公開見送りなど文化面でも締め付けが起きているという
対日圧力は効かない、むしろ日本側に追い風
・水産物輸入停止は長年続いていたため、輸出先はすでに豪州・米国・韓国などへ分散済みで影響は限定的
・旅行自粛も、オーバーツーリズムやマナー問題の観点から「むしろ続けてほしい」と皮肉
・日本は圧力に屈せず、淡々と対処すべきだという立場を再確認
産経「経済対策21兆円」—高市・片山コンビの勝負
・最大のニュースとして、産経新聞の「経済対策21兆円」報道を取り上げる
・政府が2025年度補正予算の歳出と、ガソリン税暫定税率廃止など大型減税の効果を合算し、21兆円規模で最終調整
・地方自治体や民間企業分を含めた事業規模は約42.8兆円を見込む
・トランプ政権の高関税政策の影響も見据え、景気の底上げを狙うものと説明
・財務省が規模を絞り込もうと日経などへリークしていたが、結果的に“無駄骨”になったと評価
立憲民主党・岡田質問への強い危機感
・永田町に「立憲民主党許すまじ」の空気が広がっていると述べる
・岡田克也氏の質問の本質は、突き詰めれば「台湾侵攻は中国の内政で、日本や自由社会が反対するのはけしからん」という立場だと解釈
・さらに「武力攻撃を受ける米軍は放っておけ」という、存立危機事態や日米同盟を否定する主張に近いと批判
・この立場が通れば、日米関係は終わり、台湾侵攻を呼び込み、世界戦争へ拡大しかねないと警告
岡田氏と中国“対外工作機関”の関係批判
・岡田氏が中国共産党の対外工作機関である「中連(対外連絡部)」と覚書を交わしてきた過去を問題視
・こうした政党が日本で存在する価値はないと断じる
・さらに岡田氏の実家に関係するイオンが、中国で巨大モールを開業する動きも絡め、立憲の“対中姿勢”が国益とズレていると示唆
立憲内部ですら“コンセンサスなし”
・産経(11月19日配信)を引き、立憲内部で岡田路線が一致していない点を指摘
・野田代表は「安保法制の違憲部分は現時点で見つかっていない」と述べ、岡田氏はそれを「苦しい」と批判
・岡田氏は存立危機事態の解釈などを年内に詰め、党としての立場を決めたいと言うが、
・「党内で立場も固まっていないのに、あの質問をしたのか」と不信感を強める
・この混乱こそ、立憲が国政に必要かを問う解散総選挙の大義になると主張
台湾有事は「日本の問題であり世界の問題」
・台湾は中国が一度も支配・統治したことがない自由主義圏であり、侵攻は理不尽と再確認
・日本は「中国の主張は理解・尊重するが、侵攻を認めない」という国際的立場を取るべきだと整理
・台湾が保有するミサイルが発射されれば上海などに届き、第三次世界大戦になり得るため、国際社会は必死で抑止していると説明
・G7外相会合で中国を慎しめる共同声明が出たことや、SWIFT・ドル決済からの締め出しの可能性にも触れ、中国が追い込まれていると語る
・中国の若年失業率悪化や経済の停滞が、対日強硬の背景にあると見る
補正成立→解散へ、SNS拡散を呼びかけ
・臨時国会で大型補正が成立すれば「日本を守るための解散」に踏み切れると展望
・国民は物価高対策・減税を進める政権を支持し、解散総選挙を望むはずだと訴える
・「臨時国会終盤での解散決断」「来年の通常国会前の投開票」を期待
・SNSでの拡散・応援を強く呼びかけ、安定多数を得て高市体制を盤石にすべきだと締めくくった
キーワード:解散総選挙,中国の対日圧力,旅行自粛,水産物輸入停止,対日印象操作,高市早苗,片山さつき,経済対策21兆円,補正予算,ガソリン税暫定税率廃止,財務省,立憲民主党,岡田克也,存立危機事態,日米同盟,集団的自衛権,台湾有事,中連,対外工作,SNS拡散